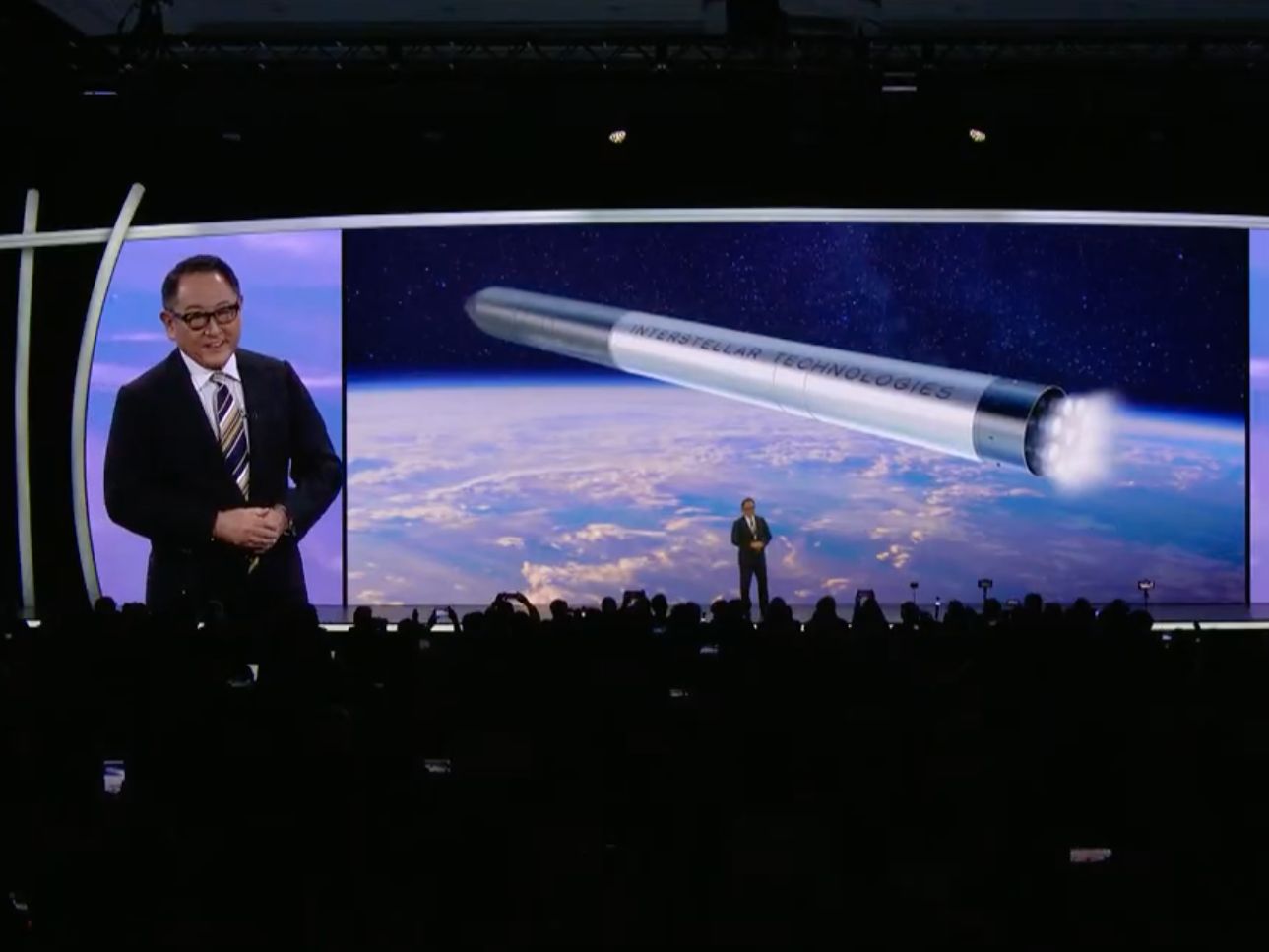特集
携帯キャリア4社の「スマホと衛星の直接通信」構想が出揃う–先行する米国の動きや課題を解説(秋山文野)
2025.05.15 09:00
日本の携帯電話キャリア4社から、スマートフォンと通信衛星の直接接続サービス(DTC)の構想が出揃った。ソフトバンクは5月8日に、宮川潤一社長が同サービスを2026年中に開始すると発表。NTTドコモの前田義晃社長も5月9日に、2026年夏に開始することを明らかにした。ただし、提携する衛星企業はどちらも非公開だ。
国内で先行するKDDIは4月10日に「au Starlink Direct」をいち早く開始している。また、楽天モバイルも4月23日に、「Rakuten 最強衛星サービス」を2026年第4四半期に提供すると発表していた。日本でも急速に立ち上がってきたDTCが実現するまでの米国を中心とした動きとその背景、課題などを整理してみる。

米国から「スマホと衛星の直接通信」が発展した経緯
Direct-To-Cell (DTC)とは、スマートフォンなどユーザーのモバイル端末と通信衛星が直接接続できる通信サービスのこと。専用端末を必要とする従来の衛星携帯電話や、IoT機器、専用アンテナを必要とする衛星通信サービスに加えて、特別な改造や外付け機器を使わない携帯電話端末で接続できるDTCサービスの活動が2017年ごろから米国で始まり、米FCCの枠組みづくりと共に急速に発展した。
ただし、日本でも構想そのものはあり、情報通信研究機構(NICT)が「地上/衛星共用携帯電話システム(STICS)」として2008年から研究開発をしたが、実用システムとしては実現しなかった。Direct-to-Cellphone、Direct-to-Device (D2D)、Sat-Mobile-Directなどと呼ばれることもあり、名称は定まっていないが、ここではDTCを用いる。
DTC発展の背景には、従来は衛星開発と打ち上げ費用のコスト課題で実現しなかった通信衛星メガコンステレーションが、SpaceXの「Starlink」の登場によって実現した経緯がある。“Starlink以前”は、衛星を多数製造して迅速に打ち上げることが難しく、衛星通信は地上から一定の方向に常に衛星が見えている静止衛星が中心だった。コンステレーションの実現により、ユーザーの頭上に次々と衛星が飛行してくるようになり、非静止衛星(NGSO)と呼ばれる低軌道の衛星コンステレーションによってカバレッジが途切れない環境を構築することが可能になった。
2017年ごろから、米国では複数の事業者が通常の携帯電話端末を用いたDTC実現を目指して通信実験などを開始していた。2022年11月、GlobalstarとAppleが共同で、地上ネットワークが利用できない場合にGlobalstarが持つ衛星の周波数帯域を使用してiPhone 14で緊急メッセージング機能を利用できるようになるサービスを発表した。超小型衛星による各社の通信試験なども進む中で、2023年3月にFCCが「宇宙からの補完的カバレッジ(supplemental coverage from space:SCS)」と呼ぶDTCの枠組みを提案、翌2024年3月に規則の大枠を発表したことで急激に市場投入が進んだ。
米空軍やNASAに技術協力を行っている航空宇宙研究組織Aerospace Corporationは、DTCを衛星通信事業者が地上向けの周波数を衛星事業者にリースして衛星事業者が接続サービスに利用する「地上スペクトラム中心型」(携帯端末のアップデートや追加の機器が不要、周波数調整が必要)と、もともと衛星通信向けの周波数帯を利用する「衛星スペクトラム中心型」(携帯端末のアップデートや追加の機器が必要、周波数調整は不要)の2つに分け、FCCのSCS文書で業界の取り組みとして上げられた企業を地上スペクトラム中心型に分類している。
現在の位置づけでは、SCSは地上のモバイル通信網が届かない山間部や海上などで携帯端末から緊急通報サービス(米国では911)を実現するために整備されている。そのため、衛星ブロードバンドサービスを置き換えるような性質ではなく、StarlinkやAmazonのKuiperといったブロードバンドサービスがこれで不要になるわけではない。
FCCの「SCS推進構想」に登場するDTC事業者
2017年設立。欧州、アジア、アフリカにサービスを展開目標。2020年にFCCに、高度725~740kmの軌道で243機の衛星を運用する許可を申請した。これまで試験機「BlueWalker」衛星を打ち上げ、2023年にBlueWalker 3衛星と改造されていない携帯電話で衛星を介した通話に成功したと発表した。2024年9月、最初の運用衛星「BlueBird」5機を打ち上げ、今後アンテナ面積を223平方メートルに拡大したBlueBird衛星の打ち上げを続ける計画。日本では楽天モバイルがサービス展開。

2017年設立。国際宇宙ステーション補給機「シグナス」を使用した通信実験の後、2019年から試験機「Lynk」2機を打ち上げ、2020年に試験機からAndroidスマートフォンにテキストメッセージを送信する実証に成功したと発表した。2022年にFCCから「宇宙セルタワー」と呼ばれる高度約500kmの運用衛星「Lynk Towers」10機の運用許可を獲得し、これまでに6機の衛星を打ち上げている。およそ1000機のコンステレーションによりテキストメッセージ、通話、データ通信サービスを展開する目標がある。
2002年設立。2019年から衛星ブロードバンドサービス「Starlink」の構築・運用を開始した。2022年に米国T-Mobileと提携し、地上ネットワークが届かないエリアでテキストメッセージサービスを利用可能にする接続サービスの計画を発表した。2024年3月にFCCから第2世代Starlink衛星の一部をDTCサービス向けに変更する認可を得た。2024年1月には最初のDTC試験機6機を打ち上げ運用を開始。通常のStarlink衛星が高度550kmで運用するのに対し、DTC向けのStarlink(現在はFalcon 9で打ち上げるStarlink v2 mini DTC)は高度300km付近で運用する。これまでに500機以上を打上げ、2025年春から日本ではKDDIがサービスを開始。

米空軍の中小企業技術革新研究(SBIR)プログラムから2019年にシード資金を獲得。2020年にタレス・アレニア・スペースと契約して通信衛星開発を開始する。2022年4月、5月にIoT向け超小型衛星「Spark-1」「Spark-2」を相次いで打ち上げる。アフリカのモバイルネットワーク事業者MTNなど各国通信事業者と提携し、IoT、5G接続サービスを目指す。
「スマホと衛星の直接通信」の課題と今後
DTCを実現する衛星は地上から300~700km上空にあり、携帯電話からすれば地上の基地局よりもはるかに距離が遠い。この条件で確実に緊急通報を含む接続を実現するには技術的課題があり、FCCは他の衛星との干渉の回避、周波数調整などを続けている。国際的な調整も必要とされ、2027年開催の国際電気通信連合(ITU)の会議WRC-27ではDTCに関する議題が挙げられている。
先行するFCCが大枠を示したものの、仕組みはまだ固まっていない状況だ。ソフトバンク、NTTドコモの2社が提携先を非公開としているのも、まだ調整の必要な部分が残っているためと考えられる。
衛星数の拡大も課題になる。1機のDTC衛星が日本などサービス対象地域の上空を通過する時間は限られており、切れ目のない911サービスを実現するには100機、1000機単位での衛星コンステレーションが必要だ。
AST SpaceMobileは2020年に申請した243機の衛星の50%を、2030年8月までに打ち上げるマイルストーン要件を満たす必要があり、1年ごとに24機の衛星打ち上げを実現しなくてはならない。1回あたり5機を打ち上げるとすれば年に5回程度のロケットを確保することになる。この面で先行しているのは、打上げ手段を確保しているSpaceXである。
さらにFCCは電波天文学との調整を大きな課題として挙げている。宇宙から届く電波を観測する施設は、人為的な電波との干渉を防ぐために通常は人口の少ない地域に設置されている。SCSの電波が広い地域で利用されるようになると、電波天文の施設と干渉するおそれもある。
FCCはSCSと電波天文の共存のために新たな規制を設けることはしなかったものの、米国立科学財団(NSF)などの提案を元に事業者が有害な周波数の干渉を避けるよう、早期に科学機関に協力して調整を行うことを推奨している。
秋山文野
サイエンスライター/翻訳者
1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員。
秋山文野
サイエンスライター/翻訳者
1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット/人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『「はやぶさ」7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員。